タイ料理に欠かせない調味料『ナンプラー』を紹介します!臭い?100均(ダイソー)にある?まずい?どこに売ってる?スーパーのどこ?体に悪い?などの疑問を解決しつつ、ひみりか家の絶品レシピも徹底解説します!
※本ページはプロモーションが含まれています。
タイ料理やエスニック料理のレシピで「ナンプラー」と書かれているのを目にする機会があるとは思いますが、なんだっけ?って感じの方がほとんどだと思います。「どんな味?」「臭いって本当?」「家族が苦手そう…」と、なかなか手に取る勇気が出ない方も多いのではないでしょうか。
実はナンプラーは、タイ料理だけでなく、普段の家庭料理にも驚くほど使える万能調味料なんですよー
独特の香りと深い旨味が特徴で、ほんの少し加えるだけで料理のコクがぐんとアップします。とはいえ、その個性的な風味や香りに戸惑う方も少なくありません。
私自身も最初は「ちょっとクセが強いかな?」と感じていましたが、使い方や量を工夫することで、今ではガパオライスやチャーハンの隠し味なんかで冷蔵庫に常備するようになりました。
ということで今回は、『ナンプラー』について、特徴(どこの国?、どんな味、保存方法、からい?)、気になる疑問(臭い?、匂いの例え、まずい?、スーパーの売り場はどこ?、体に悪い?、賞味期限切れ など)、どこに売ってる?(ダイソー、100均、コンビニ、スーパー)、ひみりか家の絶品レシピを徹底解説しまーす!
「ナンプラー」が気になっている方はもちろん、すでに使っている方にも参考になると思いますので、ぜひ最後まで御覧ください。
『ナンプラー』の特徴(どこの国?、どんな味、保存方法、からい?)

今回のおすすめ『メガシェフ ナンプラー』
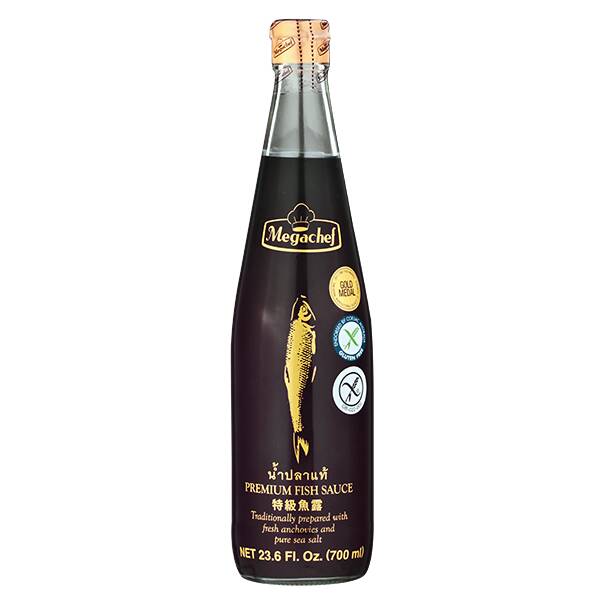
ナンプラーとは・どこの国?
- 「ナンプラー(Nam Pla)」は、タイ王国を代表する伝統的な調味料です。タイ語で「ナム(Nam)」は「水」、「プラー(Pla)」は「魚」を意味します。直訳すれば「魚の水」。その名の通り、魚から滲み出た液体を原料としています。
- 分類としては「魚醤(ぎょしょう)」の一種にあたります。魚醤の歴史は非常に古く、アジアだけでなく、古代ローマ帝国でも「ガルム」と呼ばれる魚醤が愛用されていました。
- 高温多湿な気候の東南アジアにおいて、魚を腐敗させずに長期保存し、かつ食事に必要な塩分と旨味を摂取するための知恵として生まれたのがナンプラーです。タイの家庭においては、日本における醤油と同じくらい、あるいはそれ以上に欠かせない「食卓の魂」とも言える存在です。
原材料
- ナンプラーの主な原材料は、カタクチイワシなどの小魚と塩のみ。新鮮な魚を内臓ごと大量の塩に漬け込み、半年から2年ほどじっくり発酵・熟成させます。この発酵過程で魚のタンパク質がアミノ酸に分解され、濃厚な旨味と独特の香りが生まれるのです。
- 製造工程はとてもシンプルですが、魚の種類や発酵期間、塩の質によって風味や香りが大きく変わります。上質なナンプラーは「一番搾り」と呼ばれ、発酵液の上澄みだけを瓶詰めしたもの。まろやかでクセが少なく、料理の味を格段に引き上げてくれます。
- 栄養面では、ナンプラーにはアミノ酸やタウリン、ビタミンD、ヨウ素などが豊富に含まれています。これらは骨を強くしたり、疲労回復やアンチエイジング、基礎代謝の促進など、健康面でも注目されています。
どんな味?

ナンプラーの味を科学的に分解すると、主に「塩味」と「旨味」、そして「香り」の3要素で構成されています。
- 塩味
醤油よりも塩分濃度が高く、直接舐めるとかなりしょっぱく感じます。 - 旨味
ここが最大の特徴です。魚の動物性タンパク質が分解されてできたグルタミン酸やイノシン酸が豊富に含まれており、その旨味の強さは一般的な出汁の比ではありません。 - 香り
発酵による独特の熟成香があります。生のままでは魚特有の生臭さを感じることがありますが、加熱することでその表情は一変します。香ばしく、食欲をそそる芳醇な香りへと昇華するのです1。
味の傾向としては、甘みはほとんどなく、キリッとした塩気と濃厚なコクが特徴です。
保存方法
ナンプラーは塩分が高いため腐りにくい食品ではありますが、デリケートな一面も持っています。
- 開封前: 直射日光を避け、冷暗所(常温)で保存可能です。
- 開封後: 冷蔵庫での保存を強く推奨します。
なぜ冷蔵庫なのか? それは「酸化」を防ぐためです。ナンプラーは空気に触れると酸化が進み、色が黒ずんだり、風味が劣化して生臭さが増したりします。また、常温で放置すると発酵が進みすぎて味が変わってしまうこともあります。「たびたび環境を変えない」「空気に触れさせない」ことが、美味しさを長持ちさせる秘訣です。使い終わったらキャップをしっかり閉め、冷蔵庫の定位置に戻す習慣をつけましょう。
からい?
- 「タイ料理=辛い」というイメージから、ナンプラーも辛い調味料だと誤解されがちですが、ナンプラー自体には辛味は一切ありません。
- あくまで「塩」と「魚」から作られた旨味調味料であり、唐辛子は含まれていません。したがって、小さなお子様や辛いものが苦手な方が食べる料理に使っても全く問題ありません。
- タイの食堂などで見かける、ナンプラーに刻んだ唐辛子を漬け込んだ調味料は「プリック・ナンプラー」と呼ばれ、これは明確に辛いものです。しかし、瓶詰めで売られている純粋なナンプラーは、辛味のない純粋な出汁醤油のようなものと考えてください。
『ナンプラー』の気になる疑問を徹底解説!(臭い?、匂いの例え、まずい?、スーパーの売り場はどこ?、体に悪い?、賞味期限切れ など)

臭い?例えるとどんな匂い?
正直に申し上げますと、ナンプラーの香りは独特であり、かなり強いです。初めて嗅ぐ方にとっては、「強烈な魚の干物の匂い」「イカの塩辛のような発酵臭」と感じられることが多いでしょう。中には「銀杏のような匂い」や、さらに強い表現をする人もいます。
しかし、この香りは「旨味の証」でもあります。そして重要なのは、「料理に使うと匂いが変わる」という点です。炒め物やスープに入れて火を通すと、揮発性の臭み成分が飛び、代わりに「香ばしい磯の香り」や「食欲をそそるロースト香」へと劇的に変化します。
もし匂いが心配な場合は、以下の対策が有効です。
- 加熱する: 仕上げにかけるのではなく、炒めている最中に鍋肌から回し入れることで、瞬時に香ばしさが増します。
- 酸味やハーブと合わせる: レモン、ライム、パクチー、ニンニクなどと合わせることで、匂いが中和され、爽やかな風味になります。
まずい?美味しい?

- 「まずい」と感じてしまった方の多くは、「そのまま舐めてしまった」か「入れすぎてしまった」ケースがほとんどです。
- ナンプラーは旨味と塩分の塊ですから、原液をそのまま味わうものではありません。カルピスの原液をそのまま飲むのがキツイのと同じです。しかし、適量を料理の隠し味として使うと、「魔法のように美味しく」なります。
- 例えば、カレーの隠し味に小さじ1杯入れるだけで、一晩寝かせたようなコクが出ます。豚肉の生姜焼きに少し加えるだけで、ご飯が止まらない濃厚な味わいになります。これは、肉や野菜に含まれる旨味成分と、ナンプラーの旨味成分が掛け合わさることで「旨味の相乗効果」が生まれるからです。
- 「美味しい」と感じるコツは、「最初は少なめから」。塩味も強いので、塩の代わりとして少しずつ足していくのが失敗しないポイントです。
スーパーの売り場はどこ?
いざ買おうと思っても、売り場が分からず迷うことがあります。通常は以下の場所を探してみてください。
- 中華・エスニック調味料コーナー:
オイスターソース、豆板醤、ココナッツミルクなどが並ぶ棚にあることが最も多いです。 - 醤油コーナー:
醤油の並びの端や、だし醤油の近くに置かれていることもあります。 - 鮮魚コーナー:
魚料理に合う調味料として、魚売り場の近くに関連陳列されている場合もあります。
体に悪い?

- 「添加物が多そう」「塩分が高そう」というイメージがあるかもしれませんが、基本的なナンプラーは無添加の自然食品です。
- 原料は魚と塩のみ。保存料や着色料を使わずに作られているものが多く、むしろ健康的な発酵食品と言えます。魚由来の必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルも含まれています。
- ただし、「塩分」には注意が必要です。ナンプラーの塩分濃度は高く、使いすぎると塩分過多になります。高血圧の方は使用量に気をつけてください。
- 一方で、小麦を使わないグルテンフリーの調味料であるため、小麦アレルギーの方にとっては醤油の代替品として非常に重宝されています。
賞味期限切れでも大丈夫?
冷蔵庫の奥から発掘された、賞味期限切れのナンプラー。捨てるべきか、使うべきか。結論から言うと、「未開封なら多少過ぎても大丈夫なことが多いが、風味は落ちる。開封後は状態を見て判断」です。ナンプラーは塩分濃度が高いため、腐敗菌が繁殖しにくく、腐りにくい食品です。しかし、酸化は進みます。
以下のような変化が見られたら、品質が低下しています。
- 黒ずみ: 新品の琥珀色から、醤油のような真っ黒な色に変化します。
- 澱(おり): 瓶の底に沈殿物が溜まることがあります(これはタンパク質の結晶で無害なことが多いですが、品質変化のサインです)。
- 異臭: 魚の腐ったような不快な匂いがする場合。
ある体験談では、賞味期限を11ヶ月過ぎたナンプラーは、色が黒くなり、使う気になれなかったとのことです。お腹を壊す可能性は低いですが、せっかくの料理が美味しくならなければ意味がありません。「黒くなったら煮込み料理などの加熱用に使い切る」か、思い切って新調することをおすすめします。
いしる・しょっつる・ニョクマム(ヌクマム)との違いは?

世界には様々な魚醤があります。ナンプラーとの違いを比較してみましょう。
| 名称 | 国・地域 | 主な原料 | 特徴 | ナンプラーとの違い |
| ナンプラー | タイ | カタクチイワシ、塩 | 塩味が強く、発酵香が豊か。 | 旨味と塩気のバランスが基準。 |
| ニョクマム | ベトナム | 小魚、塩 | ナンプラーより発酵度が低く、香りが穏やかで少し甘みを感じることもある。 | ほぼ同じように使えるが、ナンプラーの方が塩気が強い傾向。 |
| しょっつる | 日本(秋田) | ハタハタ、塩 | 上品な甘みと旨味があり、クセが少なめ。 | 魚臭さが比較的マイルドで、和食に馴染みやすい。 |
| いしる(いしり) | 日本(石川) | イワシ、サバ、イカの内臓 | イカの内臓を使うものは濃厚なコクと独特の強い風味がある。 | イカ由来のクセがあり、ナンプラーとは香りの質が異なるが、コクは最強クラス。 |
これらは相互に代用可能です。「ナンプラーがないからしょっつるで代用」は全く問題ありません。
めんつゆ・オイスターソース・ポン酢・白だしで代用できる?
「今すぐガパオを作りたいのにナンプラーがない!」そんな時の代用術です。
- 醤油 + レモン汁 + 鶏ガラスープの素(★おすすめ)
- 醤油で塩味、レモンで酸味、鶏ガラで動物性の旨味を補います。これが最もナンプラーの役割に近いです。
- オイスターソース + 醤油 + 塩
- 牡蠣の旨味を利用します。ただし甘みが強いので、醤油と塩で味を引き締める必要があります。
- 比率目安:醤油大さじ1、オイスターソース小さじ1/2、塩少々。
- 白だし + 醤油
- 魚介の旨味という意味では近いですが、少し上品すぎるきらいがあります。レモン汁を加えるとより近づきます。
- 薄口醤油 + アンチョビ
- アンチョビペーストを少量溶かすと、原料が同じなのでかなり近い風味になります。
めんつゆやポン酢単体では、甘すぎたり酸っぱすぎたりして、ナンプラーの代用としては少しパンチが足りません。やはり「醤油+魚介・動物系の旨味」の組み合わせがベストです。
『ナンプラー』どこに売ってる?・100均に売ってる?(ダイソー、100均、コンビニ、スーパー)

ダイソー
意外かもしれませんが、一部の大型店舗のダイソー(DAISO)では、食品コーナーに小瓶のナンプラー(100円+税)が置かれていることがあります。
- メリット: 少量サイズなので、「お試し」に最適。使いきれなくても痛手が少ないです。
- 注意: 全店舗にあるわけではなく、入荷状況も不安定です。「あったらラッキー」程度に考えておきましょう。
100均
ダイソー以外の100円ショップ(Seria、CanDoなど)では、食品の取り扱いが少ないため、見かけることは稀です。「ローソンストア100」のような生鮮コンビニ型店舗なら可能性があるかもしれません。
コンビニ
通常のコンビニ(セブンイレブン、ローソン、ファミマ)で、調味料としてのナンプラーが売られていることはほぼありません。ただし、ローソン(ナチュラルローソン)などでは、ナンプラーを使用した「グリーンカレー」や「ガパオライス」の冷凍食品やお弁当が充実しています。
「ナンプラーの味を手軽に楽しみたい」ならコンビニは正解ですが、「調味料が欲しい」ならスーパーへ行きましょう。
スーパー
最も確実な購入場所です。
- 一般的なスーパー:
中華・エスニックコーナーに、「ユウキ食品」などのメジャーなブランドのものが置いてあります。 - 業務スーパー:
ここは穴場です。本場タイから直輸入された大容量のナンプラー(70g〜)が、200円〜300円程度の激安価格で手に入ります。日常的に使うならここが最強のコスパです。 - 高級スーパー(成城石井など):
旨味が強く香りの良い、高品質なナンプラー(ゴールドラベルなど)が手に入ります。
カルディ
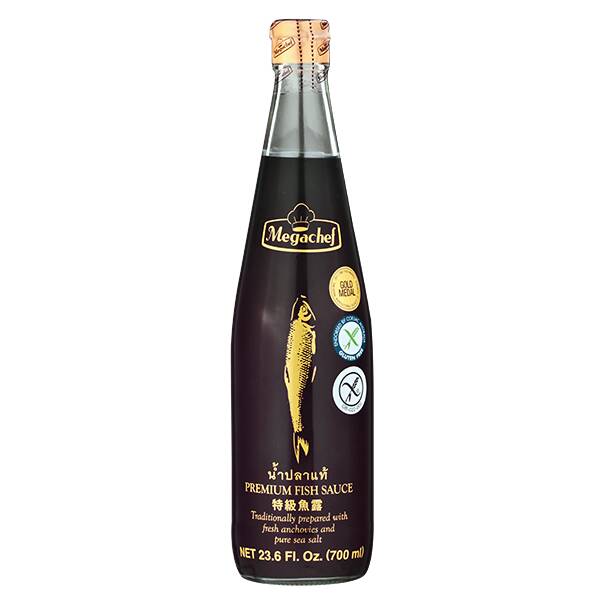
ナンプラー選びで絶対に外せないのが、カルディコーヒーファーム(KALDI)です。カルディはタイ食材の宝庫。「メガシェフ」や「ティパロス」といった、現地でも愛されている有名ブランドのナンプラーが手に入ります。
- おすすめ:
「メガシェフ ナンプラー」。260円〜300円程度とお手頃ながら、臭みが少なく、マイルドで使いやすいと評判です。初心者の方は、まずはカルディで店員さんにおすすめを聞いてみるのが一番の近道かもしれません。
『ナンプラー』を使った ひみりか家の絶品レシピ

ガパオライス
彩り豊かで 栄養満点な『ガパオライス』が おうちで簡単にできちゃうレシピです!
独特の風味が絶妙に美味しい本格的なタイ料理です!
チャーハンや肉野菜炒めの隠し味
普段の「チャーハン」や「肉野菜炒め」に、お塩の代わりにナンプラーを少量加えるだけで、コクと深みがアップします。特に冷蔵庫の残り野菜やウインナーを使った炒め物も、ナンプラーを加えると一気にエスニックな味わいになるので、いつもと違う感じになります。
まとめ:『ナンプラー』臭い?100均(ダイソー)にある?まずい?どこに売ってる?スーパーのどこ?体に悪い?などの疑問を徹底解説!

本記事では「ナンプラーの特徴(どこの国?、どんな味、保存方法、からい?)」、「ナンプラーの気になる疑問(臭い?、匂いの例え、まずい?、スーパーの売り場はどこ?、体に悪い?、賞味期限切れ など)」、「ナンプラーどこに売ってる?・100均に売ってる?(ダイソー、100均、コンビニ、スーパー)」、「ナンプラーを使ったひみりか家の絶品レシピ」について徹底解説しました!
ナンプラーは、東南アジア料理だけでなく、和食や洋食、中華にも応用できる万能調味料です。独特の香りや塩味の強さに戸惑うこともあるかもしれませんが、少量ずつ使い、加熱や香味野菜、柑橘類と組み合わせることで、誰でも美味しく楽しむことができます。
冷蔵庫にナンプラーが一本あるだけで、料理のレパートリーが広がります。本格的なタイ料理はもちろん、いつものチャーハン、唐揚げの下味、卵かけご飯の醤油代わりに数滴。それだけで、食卓に笑顔と驚きが生まれます。ぜひ、今日の食卓にナンプラーを取り入れて、新しい美味しさを発見してみてください。
今回は以上でーす。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!












